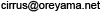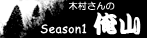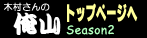山奥の岩
登山口の看板には山頂まで約2.5kmと書いてある。予想通り人で賑わっていない静かな山のようだ。能郷白山以来の山行なので、ノンビリ楽しみながら登っていこう。登山口は木の橋から。緩やかな植林隊の中をゆっくり歩いていく。足元はスギやヒノキの針葉樹の枯葉。ちょっと滑りやすいので注意だ。
ちょっと歩くと四合目。その傍らには観音様。この山には多くの観音様が祀られているようだ。こういったところでも単なる里山ではなく、歴史を感じることができるね。
ちょっと歩いただけでもなんかすごく奥深い山の中に入ってきたようだ。人っ気は無し。沢の音と時々聞こえる鳥の声だけ。

ここが登山口。山頂までは約3時間ほど。途中の屏風岩ってどんな景色だろう。

最初の木の橋で沢を渡る。

針葉樹の中の登山道。傾斜は緩やか。

間もなく四合目に到着。

所々にある木の橋。滑らないように注意だ。

たまにペンキマークも。ルートはこちらで良し。

ここでも春の息吹。

崩れた沢が登山道を横切っている。

お、ちょっと大きな橋が見えてきた。

橋は見た目よりもしっかりしてそう。KUMAクンが歩いても全然大丈夫。

目の前の橋の横に「注意!!」の看板。「一人づつあわてず、ゆっくりとお渡りください。」と書かれてある。橋は意外にしっかりとしているので、むしろ滑って転ばないように注意だ。
この先にも随所に木の橋が現れる。恐らく地元の方々が山の間伐材を利用して橋を作り、登山道を整備してくれているのだろう。これだけでもみんなに愛されている山なんだとわかる。

目の前に現れた鳥居。多分土砂によって動いたのだろう。
まだまだ沢伝いの緩やかな登山道は続く。しばらく歩いていくと人工物らしいものが見えてきた。古びた鳥居が傾いて立っている。周囲の状況から察するに、土砂で本来あったところから動いてしまったのだろう。
ここから急登かな? と思ったらまだまだ道は緩やか。ちょっと進むとこれまた観音様が祀られてある六合目だ。
この先ちょっと登山道は荒れている。苔むした滑りやすい岩が多くなり、随所で倒木が道を塞いでいるので、ある時は乗り越え、ある時は迂回しながら更に奥へ奥へと登っていく。七合目を過ぎると屏風岩の看板が現れた。左手には一際大きな岩。おー!!これはすごい。

ちょっとここから急登になるかな?

まだまだ傾斜は緩やか。ここ六合目から屏風岩まで約30分とのこと。

ちょっとこの上に乗る勇気はない・・・。

ありゃ、倒木が道を塞いでいる。

更に根元から折れた倒木。ここは迂回して。

七合目に到着。

うわ、これはどう進もうか・・・。

足元は苔むした岩。上に乗ったら滑るぞ。

途中何度も沢を渡る。沈しないように。